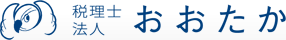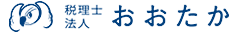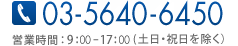役員退職所得の課税方法の見直し
退職手当は、長期間にわたる勤務の対価(給与)を一時期にまとめた後払いや、退職後の生活保障的な所得といった性質をもっています。そのため、退職所得の金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする累進緩和措置が採用されています。
しかし、この2分の1課税を前提に、短期間のみ在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取りを繰延べて代わりに高額な退職金を受け取るなどといった租税回避事例が見られるなど、問題点も指摘されていました。
そこで、平成24年度税制改正において課税方法の見直しが行われ、勤続年数が5年以下の役員等が、役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を所得金額とする措置が廃止されました。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。
この場合の「役員等」には、法人税法上の役員のほか、国会議員、地方公共団体の議会の議員、国家公務員、地方公務員が含まれます。
なお、国税庁より「特定役員退職手当等Q&A」が公表されています。Q&Aでは勤続期間の計算方法、同一年中に異なる会社からそれぞれ退職手当等の支給を受ける場合の特定役員退職手当等の判定方法、一の勤務先が同一年に使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合の源泉徴収税額の計算方法など11の事項について解説が行われています。
※詳しくは、国税庁HPをご覧下さい。
「特定役員退職手当等Q&A」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/240816.pdf